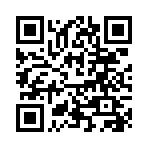お酌禁止令
2009年06月08日
 「お酌禁止令」
「お酌禁止令」
他人へのお酌を禁ずる――。長野県の板倉敏和副知事(59)の音頭で、県職員らの宴会が今春、手酌酒に様変わりした。お酌を無理強いと感じる若手や女性は少なくなく、「気を使わなくて済む」「自分のペースで飲め、酒を残さなくなった」と歓迎され、全庁的に浸透しつつある。
「お酌禁止令」のきっかけは、長野県内の蔵元が3月、県庁に日本酒のPRの要請に訪れた時の一言だった。
県内の日本酒の生産量は、97年度は1万8千キロリットルだったが、06年度は9800キロリットルにまで落ち込んだ。要請の場ではこうした現状が話題になり、県酒造組合会員の若手でつくる「若葉会」副会長の井出太(ふとし)さん(42)が「最近はお酌を嫌う若者も多い」と発言した。
これが、かねて「お酌文化」に疑問を抱いていた板倉副知事の耳に入った。元総務官僚で、在豪日本大使館に勤務経験もある板倉副知事は、「お酌の習慣は欧米にはない。嫌々飲まされるという日本酒のイメージをなくすにも、お酌はいらない」と改めて感じた。
早速、年度替わりの県幹部の送迎会の冒頭あいさつで、「お酌禁止」を宣言。その後もあいさつを頼まれれば、必ず「手酌で自分のペースで飲みましょう」と呼びかける。
職員からは好評だ。県秘書課の女性職員(29)は「つぎに回らなければという気負いや、空けなくてはというプレッシャーがなくなった」。男性幹部は「宴会後、おちょこやコップに残っている酒が減った」と語る。
酒文化研究所(東京)の狩野卓也社長(50)は「日本には、客に対して多くの食事や酒を振る舞うのが礼儀という文化があった。お酌は正しく機能すれば、もてなしや気配りの表れとして本来有用であるはずだ。ただ、無理強いしてパワハラまがいになりかねないという弊害があるのも事実。県庁など上下関係がはっきりしている公的な所で、立場の上の人がお酌禁止を言うと、酒に弱
日本の習慣は、お酌をしないといけないという規範が一人歩きしている観があるが、副知事がやめようと号令をかけて県職員の飲み会でやめ始めると言うあたりが逆に日本的な感じがするし、習慣を排することはなかなか難しいだろうと思う。
ん・・・・・とうなり声が聞こえそうですよねっ・・・
飲めない方(ゲコ)の人は少し、ほっとして・・・お酒が好きな方は・・・・・?手酌?
私はよく宴席で男性が両サイドがほとんどだ・・・コンパニオンが来てくれる席ではコンパニオンが来るのを待つか・・・
私も女性なので、気が付けば注ぎあうか・・・しかし、気が付かない方もそんな時、手酌となります・・・
なかなか手酌は、何と言うか恥ずかしいもので・・・
高山のような地元に酒蔵が16件?間違っていましたらごめんなさい・・・地元の消費量がほとんどという・・・
ここ高山では関係ない話しだねっ・・・
しかし転勤でよそから高山に支店長として来られた方々は毎年苦労してお見えのようでした・・・
http://www.emura-excel.jp